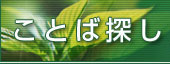■「今日のことば」カレンダー 2019年7月■
2025年 : 1 2 3 4 5 6 72024年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001年 : 11 12
| 2019-07-31 |
「人のふり見てわがふり直せ」 他人の言動によくない点を見たら、その人に注意する前に、 自分も同じようなことをしていないか確かめよう。 自分の行いには気づかないが、他人の行いは目につくので、 それを自分のよりよい行動のために参考にするというのが、 このことわざが教えるところである。(略) しかし、最近の日本人は、 このことわざを曲解していないだろうか。 他人の好ましからざる行為を見て、 「みっともないなあ、 自分はあんなことをしないように気をつけよう」 と思うより、 「他人がやっているのだから、自分もやってもかまわないだろう」 と思う傾向が強くなっていないだろうか。 「人のふり見てわがふり直せ」ということわざの機能が、 今日の日本では低下しつつあるような気がする。 かつて冗談として聞いた、 「赤信号、みんなで渡れば怖くない」 というブラックユーモアが実効的なものとして 社会に受け入れられつつあるようだ。 |
| 2019-07-30 |
マラソンは、一度リタイアすると癖がついてしまう。 そう、やめるという行為は癖になるんですね。 いったん走ることをやめてしまうと、 それ以降、意外とラクにやめられるようになる。 1回やってしまうと、同じ地点で 毎回リタイアしてしまう人もいるくらい。 心の中では「今回だけ…」と思っていても、 身体が反応してしまうようです。(略) 一度やめると癖になる。 そのことは、スポーツの世界に限った話ではないと感じます。 会社を「なんだか嫌だから」と一度やめてしまうと、 他の会社に行っても辛抱がきかなくなります。 やめることに抵抗がなくなって、 「また嫌になってきたからやめよう」と、 容易に選択できてしまうのです。 途中でやめるくらいなら、最初から辞退したほうがいい。 一度やると決めたことを途中でやめるより、最初から、 かかわらないと決心したほうがまだいいとわたしは思うのです。 |
| 2019-07-29 |
多くの人が、だれかと自分をくらべてしまう。 たとえば、トップアスリートはこのくらいのタイムで走っている、 優秀な先輩はこんなタイムで走っている、 同世代のすばらしい選手はこのタイムで走っている… そうした人たちとくらべて、自分がそこに達していないことに 気づくと、焦り、あきらめ、最後はやめてしまう… 私は人とくらべても、 「自分は劣っている、ダメだ」と思うよりは、 「よしっ、もっと頑張ろう」と思うことが圧倒的に多かった。 つねに人より下だったから、自分より上の人を見たら、 「そこに追いつこう」と思っていました。 もちろんオリンピックの選考のときや、ケガをしていたときは 不安に思うこともありましたが、最初から人より下にいたことで 他の選手に抜かれてしまった、評価が落ちてしまったと ショックを受けて落ち込むことはなかった。 むしろ、「自分はこれからずっと上がっていけるんだ」と、 つねに自分が伸びていく可能性だけを感じていたのです。 |
| 2019-07-24 |
疲れて、「包丁すら持ちたくない」という日もあります。 そんな日の晩ごはんは、潔く炊きたてのごはんのみ。 私は「お米さえおいしく食べられれば、人間なんとかなる」 と、考えているところもあって、そんな日は、 あれこれおかずに手を出さないほうがいいのです。 炊きたての土鍋ごはんに、 冷蔵庫にある常備菜をちょこちょこ添えて。 疲れた身体には、それだけでもしみわたって、 「あ~、明日からも、またがんばろうかな」 という気持ちになれるから不思議です。 |
| 2019-07-23 |
私はトップ営業マンにこのように質問します。 私「お客様から断られることなんてないのでしょうね?」 トップ営業マン「はあ?そんなわけないだろう」 私「じゃあ、断られることもあるのですか?」 トップ営業マン「当たり前だ、しょっちゅう断られているよ」 私「本当ですか!」 トップ営業マン 「営業をやっていて断られない人なんて存在しないよ」 当時これは衝撃的な言葉でした。 トップ営業マンは流れるようなトークをしてスイスイ契約を とってしまう…と勝手に勘違いしていたのですから。 勘違いに気がついたと同時になんだか少し安心しました。(略) トップ営業マンも毎日断られている、 それはダメ営業マンと変わりありません。 しかし、大きな違いがあります。 それはトップ営業マンは切り替えが早いということです。 「クヨクヨ考えればネガティブなことを引き寄せる」 ということを、結果を出す人はよく知っています。 意識的に気持ちを切り替えているのです。 |
| 2019-07-22 |
営業をしていれば、どんな人でもつらい目に あうこともあるでしょう。 ・信じていたお客様にウソをつかれた ・契約後にキャンセルになった ・途中までうまくいっていたのに、ケアレスミスで断られた などなど。 さまざまなことが起こります。 そんな時は、 一刻も早く帰って寝てしまうことをおススメします。 脳科学の本によると 「十分な睡眠をとると脳が活性化しやすくなり、 困難な問題を解決するのに役立つ」 というデータがあるといいます。 そう難しく考えなくても、誰しも、 「一晩寝たらスッキリした」 という経験をしたことがあるでしょう。 体が疲れていると心もネガティブになりがちになります。 逆に体の疲れが取れただけで気分がすっきりすることもあります。 ミスを犯してしまったらその日に反省して、 早く帰って寝てしまいましょう。 |
| 2019-07-19 |
デンマークに住む小学二年生の友人の夏休みの宿題。 1.はがきを送る 2.本を一冊読む 3.普段あまり遊ばない人と遊ぶ 4.大きなアイスクリームを食べる 5.ちょっと退屈する 6.朝遅くまで寝る 7.家族に朝ごはんをつくる 早寝早起き、ラジオ体操と言われる 日本の小学生とは大違いですね。 さらに驚くことに休むことを大切にするのは 大人も同じで、約3週間の休暇に入る直前、 「休暇を楽しめないと困るから、体調管理のために休みます」 と仕事を休む人もいるそうです。 びっくりを通り越し、開いた口がふさがりません! でも、私の夫は普段働きづめで、 年一回の家族旅行では、必ず寝込みます。 デンマーク人を見習った方がいいかもしれませんね。 |
| 2019-07-18 |
人の命は尊く、いつ延命治療を中止すべきかは 大変難しい問題です。 しかし、たった一人それを決定する権利を持っている人がいます。 それは、家族でもなく、ましてや医師でも看護婦でもありません。 いつかは必ず終末期医療に直面するであろう、あなた自身です。 日本では、無意味な延命治療の中止を求める患者の事前の 意思表明すなわちリビング・ウィルは、欧米のように 法制化されているわけではありませんが、 自己決定権は認められています。 日本の憲法学者もリビング・ウィルに書かれている 延命治療の中止の要請は、憲法が保障する自己決定権に 該当することを認めています。(略) あなた自身も必ず1回は自らの終末医療問題に直面します。 その時に備え、ぜひとも、リビング・ウィル 「終末期の医療・ケアについての意思表明書」を書いてください。 家族に口頭で伝えておくだけでは不十分です。 全ての高齢者が、「終末期の医療・ケアについての意思表明書」を 書くようになれば、少なくとも、無意味な延命治療はなくなります。 ぜひ、多くの方がリビング・ウィルを書き、家族や友に 見守られながら、やすらかに最期を迎えていただきたいと 願っています。 |
| 2019-07-17 |
運のよい人たちとつきあっていると、 不思議に幸運がやってきます。 そういう人の考え方や行動パターンが 知らず知らずのうちに身についてくるからです。 たとえばリーダーとして成功する人は、ほとんどがせっかちです。 もしあなたのまわりがせっかちで物事を翌日に延ばす習慣がない 人たちばかりだったら、どうでしょうか? あなただけ「明日やります」というわけにもいかないでしょう。 自然にせっかちな習慣が身につきます。 反対に、何ごともルーズで、物事を先延ばしする人たちばかり だったら、あなたもいつの間にかそうなってしまいます。(略) 思考パターンや行動パターンは 伝染すると思って間違いありません。 だから運のよい人とつきあうとよいといえるのだと思います。 |
| 2019-07-16 |
悲しいことに、年をとればとるほど、人によって、 「生きる姿勢」の違いが目立つようになる。 私は、目的意識や自己肯定感とともに 前向きな姿勢で年を重ねたいと思っている。(略) 女性の人生においては、 どんな時代も女友だちとの付き合いはかかせない。 そして、年をとるにつれ、前向きな人と 過ごすことがますます重要になる。 「若い気持ちが若さの秘訣」という格言をご存じ? 気持ちが若く、身体でも心でも自分を大事にする人たちと いっしょに過ごすの。 すると、どうなると思う? その結果に満足すること請け合いよ! |
| 2019-07-12 |
ダメ社員を7年間も過ごしてから、やっと目が覚めました。 「いくら自分が頑張ったとしても、相手が迷惑がる行為を しているかぎり結果は出ない。 逆に相手が求めていることをすれば自然に結果は出る」 という本質に気がついたのです。 その結果、ダメ営業マンから抜け出し、 4年連続トップ営業マンになることができました。 もしこの本質に気づかなければ、きっと今でも ダメ営業マンのままだったでしょう。 営業の商談をはじめ、仕事での打合せ、商談、会議、プレゼン …あなたがもし、これらの場面でうまくいってないのなら、 もしかしたら、それは相手が求めていないことを、 必死でやっているからもしれません。 「目の前の相手を何を求めているか?」 という本質に気がついた瞬間、人を動かせるようになり 一気に世界が変わるのです。 |
| 2019-07-11 |
「自慢」のネタがどれほどの偉業であったとしても、 自慢というスタイルで語られたとたん、 その価値は、大幅に落ちてしまうのではないだろうか。 ポイントはやはり、 「いかに自分を客観視できるか」 ということに尽きるだろう。 例えば、何かいい仕事をして人から感謝され、 自分でも満足できるとすれば、おおいに自惚れの対象になる。 それが自信になり、次の仕事へのパワーになり、また いい仕事をしてますます自惚れる、という好循環が実現する。 しかし自慢は、自信のなさの裏返しであり、 人に認めてもらいたいという主観から始まる。 相手の都合は二の次になるから、自然と人は離れていく。 それを挽回しようと自慢に拍車をかけるから、 ますます人は遠ざかる。 おおよそ自信がみなぎっている人は、 たとえひと言も発せずともその雰囲気が周囲に伝わるものだ。 自慢のネタを探すより、自画自賛できるようなワザを 身につけるほうが、よほど建設的である。 |
| 2019-07-10 |
最近気になるのは、Jポップの歌詞などでよくある 「本当の自分」という表現だ。 「本当の自分を理解してほしい」 「誰も本当の自分をわかってくれない」 などと、「なんと幼稚で傲慢なことか」と 思ってしまうのは私だけだろうか。 身もフタもない言い方をすれば、 相手から見えている自分が「本当の自分」であって それ以上でもそれ以下でもない。 お互いに、相手にどのような印象を与えているか、 影響を及ぼしているかという関係性において 存在しているのだから、それ以外に「本当の自分」を 持ち出されても困るのである。(略) 人間が成長するためには、やはり他者からの 評価にさらされる場が必要であるということだ。 そこで得られる客観的な意見というものが、 本人の社会性なり仕事力なりを鍛えていくのである。 少なくともそう考える回路を持たない人、根拠もなく 唯我独尊の世界に浸りたがる人は、 社会的に未成熟になりがちだ。 |
| 2019-07-09 |
パイロットの世界での鉄則は、 「誰かが言い出したことについては、真剣に考える」 というものです。 副操縦士が「こうじゃないですか?」 と言ってくれた言葉は、真剣に考える必要があります。 そんなことはわかっている、という態度は最低です。(略) 相手が何か言ってくれたら絶対にそれを否定しない、 言ってくれたことすべてに真剣に対処していれば、 次にちょっとでもおかしいと思ったときにも また言ってくれます。 せっかく言ってくれた言葉です。 そのなかに真理が含まれている可能性が大です。 誰かが何かを言ってくれたら、まず言ってくれたことに対して、 「ありがとう」と言うべきです。 その後、相手が言ってくれたことについて、 真剣に考えるべきです。 |
| 2019-07-08 |
何も考えずにコンピューターに上がってくる売上げ情報や 現地からのメールだけを見ていると、すべてのオペレーションが うまくいっているような錯覚に陥ってしまいます。(略) 上がってくる報告だけをうのみにすると、痛い目にあいます。 いちばんいいのは自分が直接出向くことです。 それもあらかじめ日時を伝えてではなく、突然赴くことです。 また、そのときに偉い人と話をするのではなく、 現場の末端で働いている人にいろいろと話しかけて、 情報を聞き出すことが重要になります。 相手から情報が上がってくるのを待っているだけではなく、 自分から情報をとりにいくと、思わぬことが聞けたり、 自分が想定していたことと相手が感じていたことの食い違いが 見つかったりします。 現代社会では、相手からの情報を待っているだけではなく、 自分から取りにいくというスタンスが非常に重要です。 |
| 2019-07-04 |
天国ってどんなところ? の大納得回答 ある、孫とおばあちゃんの会話。 孫「天国ってどんなところ?」 おばあちゃん「天国はすごくいいところみたいだよ」 孫「どうして知ってるの?」 おばあちゃん 「だって、行った人が、 だーれも□□□□□□のだからね」 孫「ああ、そうかぁ」 |
| 2019-07-03 |
みんながハッピーになれる呪文 我欲を捨て人類の幸福を願うことは とても大切なことであるが、 実際には、人の幸福を願う前に 自分の幸福を願いたくなるのが信条である。 上智大学名誉教授である渡部昇一氏は、こう言っている。 「人も良かれ、我も良かれ、 我は人より□□□□良かれ」 と。 これなら、無理なく実践できそうである。 |
| 2019-07-02 |
一生忘れられない恩師の言葉 人には誰でも、忘れられない恩師の言葉というのがあるだろう。 小学校5年のころだったと思う。 生徒たちが人に隠れて何か許せない行為をした。 まだ若かった担任の女教師は、悲しそうな顔をして言った。 「あなたたちは誰も見ていないと思ってこんなことを するんでしょうが、じつはいくら隠れてやっても、 いつでもどこでもちゃんと見ている人がいるんですよ。 それが誰かわかる?」 生徒たちは口々に、 「神様、仏様、お天道様、風、天狗様、幽霊、イエス様…」 などと答えたが、先生はみんな違うという。 「それはね、□□□自身よ。 どこに隠れて一人でやったとしても、□□□自身だけは、 □□□のやることをいつも見ているでしょう?」 これは子ども心にショックで、 一生忘れられない言葉になった。 |
| 2019-07-01 |
あなたが誰かに愚痴を聞いてもらうことも、 誰かの愚痴を聞いてあげることも、ときには必要でしょう。 年がら年中では困りますが、たまには愚痴のひとつも こぼしてストレス解消に努めるのは、 現代人に必須の「生きる知恵」かもしれませんね。(略) 持ちつ持たれつ、 なんとかうまくやっていく。 それこそが人間関係を円滑にする 「知恵」であり「コツ」です。 そうして、お互いが必要なときに 愚痴をこぼせる関係になれば、 いい人間関係も深まっていきます。 |