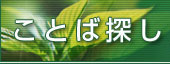■2020年01月21日の「今日のことば」■
前日のことばを見る 次のことばを見る|
ぼくがコーチングを勉強した結果、 一つ気づいたことがあります。 世間で言われているコーチングは、 こんなふうに教えると効果があるとか、 選手のモチベーションを高めるにはこういう言い方をすると 効果的だとか、ほとんどが戦略論や教え方だということです。 つまり、コーチの発信器の性能を高めれば、 よりよいコーチングができると言っている。 これは、何か違うような気がするのです。 ぼくはこれまでいろいろな指導者を見てきました。 また、ぼく自身の経験からいっても、 選手が思うように動かない、成長しないというときは、 教える側の理屈や理論が原因というより、むしろ、 教えられる側の理解力や消化力に 問題があるケースのほうが圧倒的に多い。 これは、まちがいありません。 ですから、コーチングとは教える側の発信機ではなく、 いかに教えられる側の受信機の精度を高めるかが、 ポイントになると思うのです。 つまり、コーチングの主体はあくまで、コーチングを 受ける選手になければいけないと思うのです。
誰かにコーチングするとき、教えるときには、相手の
「聞く能力」「理解力」「消化力」がどのくらいか推し量り、 相手のその能力や力に合わせることが大切だということです。 たとえば、新入社員に、 難しい業界用語や理論用語を多用して教えても、 「えっ、何を言っているの?どういうこと?」 その用語を知らない人にとってはさっぱりわかりません。 何も響きません。 わからければ、理解などとてもできないし、 良いことを聞いても、自分のものにはできず、 かえって混乱してしまい、実行もできません。 相手が自分が 「言ってることを正しく理解して実行するべきだ。 役立つことを言っている(教えている)のだから」 などというのは、大きな思い違いだということですね。 人は、どんなに良いことでも、役立つことでも、 自分がわかることだけ、理解し納得できることしか、 受け入れること、受け止めることができませんよね。 熱意みたいなもの、一部分は伝わることもあるでしょうが、 こちらが本当に伝えたいことが誤解されたり、 半端に伝わってしまうことにもなりがちです。 誰かにコーチングするとき、教えるときは、 教える側の理屈や理論を押しつけるより、相手の 「聞く能力」「理解力」「消化力」を向上させる、 精度を高めると、実行や成長に結びついていくそうです。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||