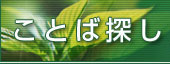■2019年04月04日の「今日のことば」■
前日のことばを見る 次のことばを見る|
「結論ファースト」は誤解も生まない。 何が言いたいかわからない話の多くは、 なかなか結論が出てこない場合、つまり重要な問いに 早めに答えていないケースがほとんどです。 あなたが次のような報告を聞いたら、どう思うでしょうか。 「雨の日も風の日も、毎日、足を運んでセールスしたんですよ。 わからない点があるって言われれば、すぐに飛んで行って、 説明したり…。そうしていると、けっこういい感じになって、 契約してもいいとまで言ってくれました。 ところが、残念ながら契約に至りませんでした」 自分が苦労したことを、アピールしたい気持ちもわかります。 ですが「自分はこれだけがんばった」のが事実だとしても、 報告を受ける相手にしてみれば、 それは最も重要な問いの答えではありません。 この場合であれば、報告を受ける側は、成約したのか、 それともしなかったのかを最も知りたいはずです。 その前に余計な情報が入ると、言い訳がましく聞こえて、 イラッとしてしまうのではないでしょうか。 また、結論があと回しにされると、誤解も生じやすくなります。
石田さんは、さらにこう言っています。
「「起承転結」の型に代表されるように、日本人は最後に結論を 持ってくる文化の中で過ごしてきました。 ですから「結論から話す」ことを意識しないと、 どうしても結論があと回しになってしまいがちです。 そもそも、人間の集中力は、徐々に落ちていくもの。 最初に結論、つまり最も重要度の高いことを伝えた方が合理的です。 結論のお手本は、新聞の見出しです。 見出しは重要な結論をズバリ言い切ったものです。 何かを説明するときは、 「これを新聞の見出しにしてみるとどうなるだろう」 などと、考えて話してみるといいでしょう」 おしゃべりなら、結論が後でも、結論がなくてもいいですが、 仕事で報告する場合は、自分の言いたいことや思い、 プロセスから話すより、結論ファーストがいいと思います。 相手が聞きたいと思っていることから話すと、すっきりと伝わるし、 聞き手もイライラせず、ストレスなく聞けます。 報告をするとき、自分の伝え方の癖がでがちですが、 意識して「結論ファースト」でいきましょう~ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||