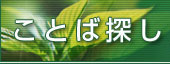■2014年11月25日の「今日のことば」■
前日のことばを見る 次のことばを見る|
《認知療法でネガティブ思考から抜け出す》
人間の脳は、ストレスを受けると、ものごとを悲観的に、 あるいは、否定的に感じる傾向があります。 このとき、考え方や感じ方に歪みが生じるのですが、 でたらめに歪むわけではないのです。 この考え方や感じ方の歪みには、 次に示すような11のパターンがあります。 1.二分割思考 すべてを白か黒か、全くか無しかといった具合に、 二者択一でとらえようとしてしまう 2.過剰一般化 何か嫌なことが起こったら、何の根拠もないのに、 それがいつも起こることだと過剰に一般化して考えてしまう 3.恣意的推論 何の根拠もないのに、将来のことを先読みしたり、 他人の心の内側について自分勝手に憶測し、悲観的な結論をだす 4.選択的抽出 記憶を思い出すとき、無意識のうちに悪いことばかりを選んで 思い出してしまう 5.マイナス化思考 良いことがあっても、日常的に起こるありふれたことでも、 悪いことだと歪めて解釈してしまう 6.すべき思考 先入観によって自分のとるべき行動を決めつけ、これによって 自分自身を追い詰めていく 7.感情的決めつけ ものごとを客観的に判断せず、そのときの自分の感情によって 決めつけてしまう 8.ラベリング 自分はダメな人間なのだといったレッテルを貼り付けてしまう 9.自己関連づけ 良くないことが起こったとき、すべて自分のせいにしてしまう 10.拡大視 自分の欠点や失敗を過大評価してしまう 11.凝縮視 自分の長所や成功を過小評価してしまう
このような11パターンがあり、人は、この中のいつくつかを
組み合わせたり重ねたりして認知の歪みを生み出してしまうそうで、 それが、自分の中で癖になっていることが多いそうです。 長い間に自分の中で思考の歪み癖ができあがり、 それを正しいこと、当たっていると思い込み、 「ほらね、私の言ったとおりじゃない」なんて思い込み、 それでかえって自分を追い込めたり悲観的にしていることもあるし、 その歪み思考に、知らずに左右されてしまっているかも しれないということです。 また、この思考の歪みは、誰にでもあるものだし、 精神的に健康な状態にあってもストレスを受けると、 何らかの形で多少認知の歪みは出てくるそうです。 ですから、この11パターンを自分を当てはめてみて、 どのパターンが多いか、それに偏っていないかを、 セルフチェックしてみるといいそうです。 それだけで、認知の歪みの芽をつみとることができるし、 いたずらに悲観的になることもふせぐことができるそうです。 自分に当てはまるパターンはありますか? 私は、4、6が多いように感じました。 これから、このことを意識してバランスをとっていこっと。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||