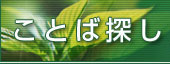■2021年03月19日の「今日のことば」■
前日のことばを見る 次のことばを見る|
「伝わるように伝わること」の 最大の難関は理解と納得とが違うことです。 そして、納得しなければ変化は起きにくいもの。 相手の言っていることを理解したからといって、 腹に落ちるとは限りませんよね。 腹に落ちなければ、相手が動くことは 期待しすぎない方がいいのです。 とにかく急いで変化を起こしたい場合、 私たちがやりがちなのは、説得です。 でも、説得は納得に直結しないのです。 コミュニケーションで大切なことは、 相手がどう行動するかの手綱はあくまでも 相手側にあるということ。 だから、相手に変化してもらいたいならば、 相手が腑に落ちるような情報になるように、 デザイン、加工して提供するしかないのです。 納得は共感と言い換えてもいいかもしれません。 共感した場合、行動に移ることが多いからです。
「現代はまさに、〝共感〟の時代」と
言われているのですが、それにもかかわらず、 説得型から脱却できない組織は多く、 そういった組織は、どんどん社会との距離が 広がって行く、と西澤さんは言っています。 さらに、 「我々(私)が言うことは、 社会一般が受け入れるべき」 という乱暴な態度では、組織であろうと個人で あろうと時代遅れのコミュニケーションであり、 もはや通用しません、とも。 先日、役所での手続きをしながら、 わかりづらく、デジタル化も半端だったので、 「もっと、わかりやすく簡略化するか、 ネットでも使いやすいようにしてほしい」 と要望したら、 「我々に言われても… もっと基幹関連部署に言ってください。 一応、我々も言ってはみますが…」 というようなことでした。 「うーん、そういう返答か」と とても??に思いました。 昨今、神奈川県で問題になった生活保護の やりとりなどもありましたが、 大きな組織ほど〝共感〟からほど遠い、 組織で働く人は、無言の圧力で、 「一般の〝共感〟など、受け止めるな」 と言われているように感じ、 一般庶民との距離はうんとあるなあ~ 遠いなあ~と実感しました。 (すべての役所がそうではないと思いますが) もっとも、自分自身を振り返ってみても、 〝共感〟できること(これが割と狭い!(苦笑))も 〝共感〟が難しいこともありますので、 〝共感〟する幅をもう少し広げる訓練は、 必要だなあって思っています~ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||