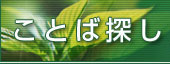■2019年11月13日の「今日のことば」■
前日のことばを見る 次のことばを見る|
論文の正しい書き方を簡単に言えば、こういうことです。 「問いかけから始まり、発見に至って、 その発見の意外さで驚かせる」 すべてを疑うことから出発して、ありとあらゆる客観的 証拠を揃えて検証し、仮説を立てて、ドーダ!まいったか! と結論を述べる。 これが論文なのです。 最初の問いかけには2種類しかありません。 1つは、今までだれも問いかけたことがなかった、 まったく新しい問い。 もう1つは、いろんな人が問いかけたけれど 確定的な答えが出ていない問い。 この2つ以外は問いかけてはいけない約束になっているのです。 これが論文のルールです。
例えば、自然科学専門誌「ネイチャー」や「サイエンス」に
投稿される大半の論文は、一次審査で落とされるそうです。 なぜなら、すでにだれかが問いかけた問いをさも、 初めて発見した問いであるかのように書いている論文が、 あまりにも多いから、だということです。 へえ…、論文とは問いかけが2種類しかないんだ、 そんなルールがあるんだ… (みなさまは、知ってましたか?) とすると…私が書いてきた論文は問いが立っていなかったな、 つまり、論文ではなかったな、そう言えば、 形だけを追っていたな、などと思いだしました(苦笑) ところで、論文について上記のような講義したら、 学生から、こんな質問がでたそうです。 「そんなことを言ったら、この世で後から 生まれた人間の方が損じゃないですか?」 なるほど、そうですよね。 先人の方が、新しい問いができそうだし、 いろいろな人が問いに取り組んでいるとすれば、 もう相当量な論文が世に出ているだろうし。 でも、鹿島さんは、一見するとそう思えるけれども、 私たちは常に変化し、世の中のシステムも変化しているので、 新しい問いはいくらでも生まれるし、答えも変化していくから、 論文の問いは永遠にある、と言っています。 それらを見つけ出すのがきっと素晴らしいのですね。 自分だけが作りうる新しい問い、 自分だけが見つけうる新しい答え、 そんなものを探し出していくのも楽しそうだ、 難しく考えず、別に発表しなくてもいいしね、 なんて思ったしだいです(笑) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||