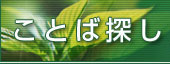■2016年10月14日の「今日のことば」■
前日のことばを見る 次のことばを見る|
家庭の習慣が違うのは当然です。 家庭によってしつけていることとしつけてないことがありますから。 だから、もし「この子しつけられてないなぁ」と感じることがあったら 「悪いけど、うちではこうしているからね、こうしてちょうだいね」 と言ってあげればいいんです。 「うちでは守ってくれる?」とよそのお母さんに言われれば、 子どもは「ハーイ」と言いますよ。 そして、それがその子にとっては新鮮な体験になるんです。 あまり走り回って悪さをするようであれば、 「ちょっと!いい加減にしなさいよ!これこれはいいけど、 こういうことはやらないでね」と、はっきりいっていいんです。 いえ、言わねばならないんです。 地域での子ども社会がなくなった今、それなりのしつけを きちんきちんと家庭内で受けている子もいれば、 しつけをされていない子も必然的に増えています。 だから、なるべくいろんな家に出入りして、 そこでもちゃんとしつけてもらうということが必要です。 そうしないとしつけなんてうまくいきません。
今日のことば、みなさまはどう感じられたでしょうか?
育児、保育の専門家の汐見さんは、さらにこう言っておられます。 「日本のしつけには弱点があります。 公共の場所では公共の論理に従わねばならない、 という部分が抜けているのです。 電車の中では大きな声を出しちゃいけない、 人に迷惑をかけちゃいけない。 そう注意することこそがいちばん大切なしつけだと思うのです。 そういう状況に抗議の意味もかねて、 子どもにはみんなで社会でのルールを教えてやるべきだと 私は思っています。 もちろん言い方には気をつけなければなりません。 頭ごなしに言わないことが大事なんです」 遊びに来た、よそのお子さんを注意をするとき、 よその子の家庭のしつけを否定せず、注意することが大切だそうです。 例えば、 「そんなことをやって、お母さんなにもいわないの?」 「まったくしつけができてないんだから」 と、言うのはよくなく、 「我が家では、こう決めているのよ。 だから、うちにきたら守ってね」とか、 「うちでは、こうしてほしいの。 そのほうが、気持ちが良いし、楽しいからね」 と、こちらの決めごと、ルールだと言う方がいいそうです。 そこでの体験が、子どもに、 「家ではやってもいいけど、ここではやってはいけない」 「こんなルールもあるんだ」「こんなこともあるんだ」 などなどいろいろなことを考えさせるきっかけにもなるそうです。 子どもは、地域のみんなで見守り、公共のルールを教えたり、 人間関係を体験させたりすることが、大切なのだなぁと思います。 そうわかっていても、どうしていいかわからないし、 余計なお世話ではないかと思ってしまうし、 今どきは、注意してその親に何を言われるかも怖いし、 大きな子だと何をされるかわからない怖さもあるので腰が引けます。 そこで自分なりに考え、地域で出会う子どもたちには、 できるだけ、明るく挨拶をしています。 「おはよう」「こんにちは」「お帰りなさい」などなど。 いい大人が挨拶くらいちゃんとできないとね、と思って(笑) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||