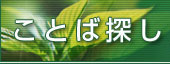■「今日のことば」カレンダー 2016年7月■
2025年 : 1 2 3 4 5 6 72024年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001年 : 11 12
| 2016-07-28 |
もしも、「仕事ができないと思われるのが怖い」という 「恐れの眼鏡」をかけていたならば、 「どうせできないヤツだと思われているんだ」 と落ち込んでしまうでしょう。 「人から嫌われるのが怖い」という 「恐れの眼鏡」をかけていたならば、 「上司は私を嫌っているんだわ」と思うかもしれません。 「私は完璧に仕事をしないと受け入れてもらえない」という 「恐れの眼鏡」をかけていたならば、 「完璧でない私はダメ人間だ」と思ってしまうでしょう。 たとえ、上司が心の中では、 「あなたに成長してほしい」と思っていたとしても。 「恐れの眼鏡」で見ると、世界は敵だらけです。 みんな私を批判しているように見える。 みんなが私を拒絶しているように見える。 みんなが私を受け入れてくれない。 |
| 2016-07-27 |
未来は平気で現在を乗っ取るもの。 未来のことばかり心配していると、 「今」という時間は、 「未来について心配する時間」になってしまうのです。 そして、そんなふうになると、 「今」目の前にいる人にやさしくしてあげるのが難しくなったり、 目の前の人のよいところに目が向きにくくなったりするものです。 愛することも愛されることも難しくなってしまいます。(略) 未来が現在を乗っ取ってしまっているようなときは、 間違いなく、未来を「恐れの眼鏡」で見ています。 そんなときには、頭が未来に行ってしまって、 「未来」を通して現在を見てしまうのです。 現在に生きているようでいて、生きていないようなもの。 だからいろいろと苦しくなるし、愛に心を開けなくなるものです。 |
| 2016-07-26 |
生きていれば、必ずつらいことがある。 それが人生。 苦痛の中にいるからこそ、品性はでてくる。 人生に夢や希望を持てないようなら、一度、 がん哲学外来や哲学カフェに足を運んでみたらいかがでしょう。 そうでなかったら、 自分よりも困っている人を探しに行ってみたらいい。 マイナス×マイナスはプラス。 本当に苦しんでいる人が、苦しいにもかかわらず、 がんばっている姿に人は感動を覚えます。 もっと強く生きていこうと勇気づけられます。 同時に自分はまだまだと痛感させられます。 自分はいま苦しい状況にある。 にもかからず笑う。 笑うことで悩める人を慰めることができます。 患者さんの姿に学ぶことは意外なほど多い。 |
| 2016-07-22 |
私たちに必要なのは正論よりも配慮です。 正論はときに相手に心に冷たく響くことがあります。 必死にがんばっている人に 「もっとがんばらないとダメだぞ」 食欲のない人に 「もっと食べないと元気になれませんよ」 余命告知を受けたばかりの人に 「あきらめたら負けですよ」 どれも正論です。 間違ってはいません。 しかし、受け取った相手はどう思うでしょうか。 私たちは冷たいものよりも温かいものを求めています。 正論は二の次です。 相手の心を慮(おもんばか)って 温かい言葉を投げることが肝心です。 万が一、相手が間違っていたとしても、 頭ごなしに否定しないこと。 このときもやはり正論よりも相手に対する配慮が優先です。 |
| 2016-07-21 |
「どこかに、幸せがある」 と幻想を抱くと、自分は幸せじゃない、 とあなたは思うことでしょう。 幸せの中にいる人は、自分の幸せを その目に見ることは出来ないのだから。 誰とも比べずに、 私は幸せの中にすでに生きていると 信じてみてください。 |
| 2016-07-20 |
その人の成長の糧になるような叱り方ができれば、 こんなにすばらしいことはありません。 たとえば、よくミスをする人に、 「ミスばかりするな!」ではない言葉で、 相手の成長の糧になるように叱ってみてください。 次のような言葉では、どうでしょう。 「ミスをしたら、必ずばん回しろ!」 「どんなミスでも、貴重な体験になる、次に生かせ!」 「ミスするごとにたくましくなれ!」 このように、ミスを前向きに位置づける言い方にすると、 ミスばかりしていることを指摘しながら、 叱責はそれほど厳しくは聞こえません。 ミスを成長のきっかけ、レベルアップの肥やしにするように、 呼びかけることで、明るい叱り方になっています。 その一方で、「これからは、同じようなミスを二度とするな」 というメッセージも伝わります。 |
| 2016-07-19 |
「もう、最悪!」 「つまんね-」とか日々言ってるけど、 映画館で、隣にいる恋人が、 映画の感想を途中で言い始めたらどうする? 「待て待て、最後まで見なきゃ、分からないでしょ?」 って言うよね。 映画は、映画が終わった時に、その感想を言えます。 人生もきっと、そうなんでしょう。 僕たちが人生の観想を言うには、 少し早すぎるようです。 |
| 2016-07-15 |
すべての人がそれぞれの「事情」を抱えています。 持って生まれたもの、育った環境、現在の生活や仕事の問題など、 その人の事情は基本的には本人にしかわかりません。 どんな人も、それぞれの事情の中で、できるだけのことを しながら生きています。 周りから見て「努力が足りない」と思うような場合でも、 本人は自分の事情の中で最大限の努力をしているものなのです。 人を変えることができないのはこれが理由で、 相手はすでに最大限の努力をしているので、 人から言われて変わるほどの余裕がないのです。 相手への役割期待を考える際には、 「本人にしかわからない事情があって、その中でベストを 尽くしている姿が現状なのだな」という目を持つようにすると ストレスがたまらなくなります。 |
| 2016-07-14 |
日本で生まれ育った人は何かについて考えたり語ったりするとき 知らず知らずのうちに「どこかに正解があるはずだ」と 思う傾向があるようです。 でも意見には「絶対解」などというものはありません。 意見はそれぞれの人が自分で考え出すものです。 人間が頭の中で考え出すものである以上、一人ひとりの意見は それぞれ違っていて当然です。 ですから、意見を言うときには 「間違っているかもしれないんですけど…」などと 思わないでください。 「間違った」意見というものは「正解である意見」が 存在して初めて成り立つものです。 大方の人が賛成(または反対)する意見、というものは あるかもしれませんが、「正解」としての意見など本来ないのです。 誰かがあなたとは違う意見を言ってきたとしても、 「自分はダメなんだ」とは思わないこと。 |
| 2016-07-13 |
苦しいことや困ったことに出会ったら、 この言葉を口に出してください。 大きな壁にぶつかったり、悩みやトラブルが生じたとき、 「意味がある」 「試されている」 という言葉は大きなパワーをくれます。 この言葉を口にすると、不思議と その後に否定的な言葉がでてきません。 ふつう、なにか問題が起きたときに、 「なんでこんなことが起きるんだ」と口に出すと、 「もうやってられないよ…」と言葉が続きます。 なにをやってもうまくいかないと、 「なんだかうまくいかないなぁ」と口に出してしまい、 「ツイてないよ、まったく…」と続いてしまいます。 そんなときに、この言葉を使ってみてください。 |
| 2016-07-12 |
悪口ばかり言う人。 「えっ?」「そうなの?」「へえ?」「本当?」と つねに驚き、質問し続けます。 間違っても「そうなんだ」などと同調してはいけません。 悪口を言う人に相づちなどを打とうものなら、 「あの人も言っていた」となるからです。 悪口を言う人というのはどこかで後ろめたく思っているので、 責任を分散させようとするものです。 自分一人で悪口を言っていると、責めはすべて自分が かぶらなくちゃいけないので、その話に相づちを打った人を 勝手に共犯者にしようとします。 その術中にはまることは避けたい。 とはいえ「そんなことはないですよ」と反論すると、 話しが長くなって面倒くさくなる。 そこで、驚きと質問です。 悪口を言っている人にとっては否定された気がしないし、 こちらとしても肯定や共感でないということを示すナイスな道具です。 そして、最後は「フーン」で終わります。 |
| 2016-07-11 |
コミュニケーション能力が高いというのは、 他者の歓心を買うのに長けているということではありません。 人と人はわかり合えなくて、誤解もたくさんあって、 たとえ同じものを見ていても食い違いが起きてしまう。 それが常なる状態であるという前提に立ったうえで、 いま何が起きているかを観察する力が コミュニケーション能力なんだと思います。 どうしてこの人はそういうことをするんだろう? なぜこんなことを言うんだろう?と。 コミュニケーションに必要なのは、相手を観察する力です。 |
| 2016-07-08 |
人の意見にはたいてい、背景や思い入れ、葛藤、 本人にとっては当たり前だからこそあえて口にしない前提など、 目には見えない多くのものが含まれています。 この中で特に見えづらいのが、前提です。 背景や思い入れ、葛藤は、よい質問をしているうちに 見えてくることがけっこうありますが、前提は、 本人にとっては当たり前のことだからこそ、 見えづらいのです。 |
| 2016-07-07 |
自分が決めたルールで、 自分が苦しむって、 なんかバカらしくない? 「こんなことをしてはいけない」 「あんなことしてはいけない」 いけない、「生けない」、いけない。 全部、あなたが勝手に決めたんだ。 そんな人生のことを、 「生きている」だなんて、 言えるだろうか? |
| 2016-07-06 |
「3番テーブル、空いたお皿があるだろ! もっとこまめに、サービス回れよ!」 新入りのウエイトレスが、店長に怒られていた。 それでも、まだ不慣れな彼女は、客がいるテーブルには、 なかなか行けず、レジの前でモジモジしていた。 僕が料理を取りにテーブルを立った時、「今だ!」とばかりに 彼女は空いた皿を下げに来て、僕が席に戻る前にそそくさと 厨房へ逃げ込んだ。 僕は、そっちのほうが好きだった。 「空いているお皿、お下げしましょうか?」 と何度もテーブルに来る店長よりも。 僕は、彼女のやり方のほうが、好きだった。 店を出る時、彼女は、お皿が山盛りの僕のテーブルを指さした 店長に怒られていたが、落ち込まないで良い。 あなたの「やり方」のほうが、好きな人が、絶対にいる。 誰かのやり方だけが正しいとは、限らない。 |
| 2016-07-05 |
愛着のあるものを捨てるのは、ときには痛みを伴います。 研究グループ(※)の論文によると自分の持ち物を手放したとき、 「痛み」に関連する脳の2つの領域、「前帯状皮質」と 「島皮質」が反応することが確認されています。 ものを捨てるには、多少なりとも痛みを伴うのです。 しかし、最初は躊躇、逡巡してなかなか捨てられないものでも、 思い切ってゴミ袋に絞り込むと、その先はさほど迷わなくなり、 ものをポンポン捨てる決断が早くなっていきます。 「ものへの執着、こだわり」よりも、 「捨てる快楽」のほうが、強くなってくるのです。(略) 何かを決めるには、捨てる、切り離すといった痛みを 避けて通ることはできないようです。 ※アメリカイェール大学らのグループ 強迫性障害の亜型である 「ため込み症候群」の脳画像研究) |
| 2016-07-01 |
私は、ほめ言葉というものはたくさん覚えるよりも、 いくつかの効果的なほめ言葉をしっかり使いこなせるほうがいい、 と考えている。 中でも私が重宝しているほめ言葉を9個選んでみた。 これらの言葉は比較的どんな場面でも使いやすく、 自分なりに使いこなせるようになれば、 味わい深い「ほめ言葉」になるだろう。 1.いい顔になったね 2.それが君の取り柄だ 3.大事なところでよく頑張った 4.君は貴重な存在だ 5.○○さんがほめていたよ 6.いいセンス持っているよね 7.君たちと一緒に仕事がしたかった 8.最初からこれだけできれば大したものだ 9.ありがとう |