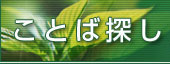■「今日のことば」カレンダー 2007年6月■
2025年 : 1 2 3 4 5 6 72024年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001年 : 11 12
| 2007-06-30 |
運勢が開けてくるか、もう答えは分かり切った話しです。 最後のどの案を採用するかを決めるのは自分だ。 その覚悟があってこそ、人生運がよくなろうというもの、 運勢が開けようというものです。(略) 覚悟さえあれば、占いに悪い結果がでても、 現実がそうならないようにいくらでも変えていけます。 結果が悪い占いを気にする暇があったら、 どうすれば良くなるように変えていけるかを考え、 行動していけばいいだけの話しなのです。 それが占いの本当の活用法です。 |
| 2007-06-29 |
思っているかもしれない。 もしそうなら、白か黒か、2つに塗り分けるのが 好きなタイプだろう。 残念ながら、世の中の人生のあらゆる条件を、 このようにはっきりと色分けするのはとうてい無理だ。 複雑な性質を持つできごとを、2つの分類にきっちりと はめ込むことなどできはしない。 確かさを望むことは、確かに健全なことではある。 しかし、不確かであることこそ人間らしいのだと受け入れ、 そのことで悩まない方が、心の健康にはいい。 だから、確かなものを求めるのはやめて、 不確かさを受け入れよう。 |
| 2007-06-28 |
何もしないことをお勧めする。 次にすることがわからないのなら、有意義な行動の前に、 見出すべきもの、あるいは学ぶべきことが あるのかもしれないからだ。 そうした状況では、一歩下がって(ほんの一瞬でも) 内面を向き、内なる大いなる力に導きを求めるのだ。(略) もし何かをしないでいられないのなら、 心を安らかにさせることだ。 それは何につけても大切な基盤に立つことになるから、 正しい行動はついてくるだろう。 怖れやパニックで行動する者は、単に闇を深くするだけだ。 しかし、安らいだ心で行動する者は、内なる知という 静けさからくる言葉や行動で、光を増すのだ。 安らぎから発する行動と、思考に責め立てられた行動には 芳しい違いがある。 |
| 2007-06-27 |
人にも出来事にも。 レッテルを貼ることが、世界を知ることだと、 誤解してしまっています。 レッテルの中身については、触れないままで。 だから、内気な人、冷たい人、優しい人、頭のいい人、 それ以外のその人に触れる機会を失ってしまうのです。 そればかりか、もっと困ったことに、レッテルを貼ることで、 その人を理解したような気になってしまうのです。 実際には、あなたは、あなたの頭の中につくりあげた、 その人のイメージを見ているだけだというのに。 レッテルは便利なものですが、 レッテルはその人ではないことを、忘れてはいけないのです。 |
| 2007-06-26 |
もっと大きく、もっと多く、もっと高く、 と人をむやみに駆り立てる。 「周囲の期待」という呪縛もまた、 必死でそれにこたえようとする人を、 本意とはちがう道へひた走らせる場合が多い。 しかし、忘れてはならない。 自分がほんとうに求めるもの、大切にすべきものを 見失ってしまったならば、 真に実のある人生は築けないのである。 あなたにとって、人生の「成功」を測るモノサシ、尺度、 とは、いったい何だろうか? |
| 2007-06-25 |
あなたの言うことを、おとなしく聞かせる 魔法の文句を披露しよう… 「あなたがそう思うのは、もっともです。 もし私があなただったら、やはり、そう思うでしょう」 こう言って話をはじめるのだ。 どんな意地悪な人間でも、こういうふうに答えられると、 おとなしくなるものだ。 |
| 2007-06-24 |
必要があるわけではなく、自分のさまたげとなるものを、 すべて手放していくように誘います。 世の中は、成功するということは得ることであり、 所有することであると教えてきましたが、 ものを集めれば集めるほど、私たちは自分自身を知らず、 安らぎからどんどんかけ離れていくことに気づきます。(略) 所有物や地位や学位で自分を証明したり、 守ろうとするのをやめたとき、 私たちはあるがままの姿に、美と価値を見出し始めます。 そうすると、軽くなることに大きな喜びを見いだします。 なぜなら、軽くなるればなるほど、 高く飛翔することができるからです。 幸福をさまたげる所有物や活動や人間関係を手放すと、 自由を得ることができ、人生の中のシンプルなことに 感謝を感じるようになります。 |
| 2007-06-23 |
「しかる」という行為は、本能に訴えることで効果が大きい。 けれども、しかり続けると 防御作用によって耐性ができてしまう。 だから、何回もしかられていると、 聞く耳を持たなくなってしまうそうです。 「しかる」のはたまにすると効果的ですが、 しかり続けると、かえって教育効果が なくなってしまうんですね。 その逆の「ほめる」という行為は、本能でなく 脳の前頭前野に働きかける高度な行為なので、 1回では足りないそうです。 繰り返し行わないとダメらしい。 ほめ続けることによって効果がでてくるんです、 というお話を川島先生はされていました。 そこで私たちは、 「ほめること9割、しかること1割」 にすることをめざしているんです。 |
| 2007-06-22 |
今までの経験(つまり、今までに蓄積した全て事柄)に マッチしている考え方を「正しい」と思う傾向がある。 たとえば、本書を読んでいて、 今まで自分が思っていたことと同じ考え方が出てくれば、 「そのとおり!この人の言うとおりだ」と思い、 「素晴らしい本だ!」ということになる。 だが逆に、今までの経験に合わない考え方には 反発を感じ、たとえば「これは違う!」 「そんなふうに考えることはできない」 「そんなに簡単なはずがない」と思うようになる。 だが、「こんな考えはダメだ」と思ったときこそ、 とくに注意深くなる必要がある。 なぜなら、そのときこそあなたが今まで 見聞きしたことのない考え方と直面しているからである。 それは、あなたが今まで知らなかった思考法なのだ。 あるいは、知ってはいても、 そういう生き方をしてこなかったのだ。 だから、これから新しい生き方をしようと思っているなら、 そうした考え方にぶつかるたびに、 関心をもつことが大事なのである。 その考え方のなかに、あなたの将来の成功のカギが 隠されているかもしれない。 |
| 2007-06-21 |
どちらかが間違っているからではなく、 双方が自分の価値観に従って生きているからです。 いわば、どちらも「理想を追い求める人」なのです。(略) 意見の違いだけに目を向けていては、対立は解消できませんが、 意見の違いの根底にある夢や目標、願望に目を向けることで、 理解の糸口が見つかります。そうした夢や目標は 「隠された意図」と言い換えてもいいでしょう。 意見がぶつかったとき、相手の主張を 頭から否定するのではなく相手の立場で考えてみる。 相手の「隠された意図」をさぐってみるのです。 対立そのものを解決しようとするのではなく、 それぞれの主張の背後にある 価値観や目標を理解し合うことです。 |
| 2007-06-20 |
どんなことでも、期待しすぎるとがっかりするものです。 期待の大きすぎる人は、毎日失望しながら 生きていかなくてはなりません。 わたしと夫はよく試写を観にいきますが、 そのときは批評など何も読まずに白紙の状態で 見るほうが楽しめるような気がします。 逆に「最高だ!」という批評を読んでから観にいくと、 「それほどでもなかった」と思うことが多いのです。 休暇旅行、パーティ、レストランの食事もみな同じです。 人生についても、やはり同じです。 期待や要求を何も持たずに、あるがままの今をエンジョイする… それがもっとも幸福な生き方かもしれません。 |
| 2007-06-19 |
うまくいかない場合には、後悔や不安に溺れるより、 すぐに前向きな期待をもって気分を盛り上げよう。 「もっといいプランがあるに違いない」と。 その時点ではほかのプランの内容はわからないかもしれないが、 自分にとってもっといいものが用意されていると 信じることはできる。(略) きっとわたしという船の艦長である神様は、 別の方向に船を向けようとしているのだ。 それがどこかわからなくても、こころをオープンにして、 積極的に認めようとするなら、 いつかわかるようになるとかたく信じている。 |
| 2007-06-18 |
してこなかった人はたくさんいる。 そういう人だって背筋を伸ばして 「やってみよう」と言えばいいのだ。 そうすれば今までプラス・ファクターをさえぎっていたものが、 取り除かれ、体中に力がみなぎってくるのがわかるはずだ。 この力は、最初の一歩を踏み出した瞬間、あるいは、 最初に前向きの思考をはじめた瞬間にみなぎりはじめる。 どんなに一生懸命夢を描いても、 どんなにはっきりした目標をかかげても、 実際に自分の足で実現への一歩を踏み出さないかぎり、 力がわいてくることはない。 |
| 2007-06-17 |
たやすいことではありません。 ましてやそういう習慣と縁を切ることはもっと大変です。 自分の問題を周りの人たちや環境のせいにしたところで 事態はいっこうに改善しないことくらい、 あなたもすでに気づいているはずです。 あなたの人生を変える力をもっているのは、 あなたしかいません。 うまくいかない行動パターンから抜け出すには、 そういった自己責任の意識に目覚める必要があります。 自分の人生を改善することを目標にしてください。 |
| 2007-06-16 |
そう悟ることが重要です。 生きているうちにはたくさんの間違いを犯すし、 誤った情報に基づいて行動したり、 ばかなことをすることだってあるでしょう。 それでも、自分なりにいちばんいいと思うやり方で、 生きていることに変わりはないのです。 「いよいよ人生を棒に振るチャンスだ」などと、 思う人はいないのですから。(略) 他人を責めても何の解決にもならないことを あらためて知りましょう。 |
| 2007-06-15 |
やっぱり忘れてしまった、という経験はありませんか? 心は「忘れる」という行為から遠ざかることはできません。 「覚えておく」という行為に近づくことはできるけれど、 そのためには「これを覚えておきたい」と 考える必要があるのです。(略) 心は考えたことの逆を実現させようとは決してしません。 したくでもできないからです。 だから、サッカーの選手に向かって「ミスするな」と 叫ぶのは、ミスを誘っているようなものだし、子どもに 「おばあちゃまの骨董品の壺を割らないで、一万ドルもするのよ」 と言えば、みすみす災いを招くことになるでしょう。 |
| 2007-06-14 |
「どんな状況においても、いろいろな選択肢が考えられる」 ということだった。(略) 人生に行き詰まったら、 「今、どんな選択肢を考えることができるだろうか」 と自分に問うてみることである。 そうすることによって、新しいステップが目の前に、 出現することがよくあるし、 自分の本当の気持ちもよくわかる。 |
| 2007-06-13 |
矛盾している人がいます。 そのときは、その人の言葉を聞くのをやめて、 その人の行動だけを見ていると、 その人の本当の目的がわかります。 言葉が、その人の本当の気持ちを表しているとは限りません。 自分への非難や攻撃を避け、あるいは相手を 自分の思うように動かすために使われることがあります。 また、こうありたい、あるいはこうなりたいという 決意や願望を表すのにも使われることもあるのです。 他方、行動は、短期的には、あるいは少数の人の前では、 意識的にとりつくろうことはできますが、 長期的に、また多数の人に対して ごまかすことはむずかしいのです。 |
| 2007-06-12 |
お互いに助け合えるネットワークを作る。 誰を知っているかではなく、 誰に知られているかが重要です。 |
| 2007-06-11 |
はじめから自分につまらぬレッテルを貼るな! 「できっこない、やれっこない」を 捨ててはじめて先が見えてくる。 できない理由より、 「できる理由」を考える人は、 かならず伸びる。 (小タイトル一部抜粋) |
| 2007-06-10 |
何かを与えたりすることができなくても、それでいいのです。 私たちが笑顔で暮らし、自分のことを好きでいられて、 思いやりの気持ちが自然と先立つように生きることができれば、 世の中はどんどんよくなるはずだからです。 不幸な人や、満足でない境遇の人など 放っておきましょう、と言っているわけではないのですよ。 プラスの力が大きくなればなるほど、 マイナスワールドもプラスのほうへ 繰り上がってきやすくなるのです。(略) その目に見えない波動が、穏やかでない人の心を ひとつ安らかにするこができるならば、 それは充分な愛や奉仕なのです。 |
| 2007-06-09 |
どういうことかと言うと、例えば先に私は 「多くの不安は無駄である」と書いた。この本を読んで、 なるほどそういうことか、と思ってくれたら、 適宜その考え方を使ってもらいたいと思う。(略) 「ああ、これはいい考えだな、ステキな考えだな」 と思ったのなら、その考え方を1回でもいいから 実際に使ってみて欲しいと思う。(略) それはもちろん、本に限らない。 友人が言ったことでもいいし、映画やテレビドラマで 役者さんが言っていた台詞でもいい。 自分の琴線に触れた言葉を覚えておいて、 随時使ってみるだけでも、 人生はいいほうへいいほうへと向かっていくと思うのだ。 |
| 2007-06-08 |
バッテリーが空で走れるだろうか?(略) とにかく、「自分をよみがえらせてくれるもの」に 敏感になることだ。 毎日の生活の最低でも1つ、自分にエネルギーを 与えてくれるものを組み入れよう。 自分自身をチェックして、エネルギー切れの信号が でていないか注意しよう。 疲れやストレス、頭痛や意欲の低下が危険サインだ。(略) 充電の時間がないと言いわけをしている自分に気づいたら、 自分のためを考えるのは自分しかいないのだ、 ということを思い出すこと。 |
| 2007-06-07 |
5人家族の中で育った、14歳になる娘さんの一言である。 話題がふと「利他主義」におよんだとき、その意味を のみこめない小学生の妹に彼女はこう説明した。 「それはね、 自分よりも相手の得を先に考えてあげることなの。 そうすることで、自分もうんと得をするのよ。」 真意をつかめないでいる妹に、彼女はこう言葉を加えた。 「私たちがね、みんな自分の得ばかり考えていたら、 自分の得を考えているのは自分1人でしょ? でもね、たとえばうちの場合、 5人家族がみんな相手の得を考えたとしたら、 自分の得を考えてくれる人が、 4人もいることになるのよ!」 |
| 2007-06-06 |
幸せな人たちと付き合うと、幸せについて学ぶでしょう。 だらしない人たちと付き合うと、 自分の生活もだらしくなくなるのです。 熱意あふれる人たちと付き合うと、自分も熱意あふれてくる。 冒険好きな人たちといると、ついつい冒険好きになるし、 裕福な人たちといると、刺激を受けて 自分も裕福になろうとする、これが人間です。 つまり、私たちは人生に求めるものを自分で決め、 それに応じて仲間を選ぶ必要があるということです。 あなたはこんな風に言うかも知れません。 「それはひと苦労だ。気まずい思いをするかもしれない。 今の仲間のうち何人かは、気を悪くするだろう」 その通りです。 でも、あなたの人生がかかっているのですから。 |
| 2007-06-05 |
批判していたことがありました。 それ以来、人に対して批判的な気持ちが起こったとき、 それは「嫉妬」なのか、正当な意見なのかを チェックするようになりました。 特に感情的になっているときは要注意です。 心の中に「嫉妬」があってはの発言は、 他人への説得力がないし、後味も悪いものです。 他人を「うらやましい」とか「ねたましい」と思ったときは、 悪口を言ったりして他人の足をひっぱるのではなく、 自分のやりたいことにチャレンジするというような、 前向きのエネルギーに代えていくとよいですね。 |
| 2007-06-04 |
相手に関心を持つことが大事」 私の30年の研究からも、 これ以上のアドバイスはないと、断言できます。 デール・カーネギーは、 「他人の関心を引こうと2年間努力するよりも、 他人に感心をもとうと2ヶ月間努力する方が、 たくさん友だちができる」 と書いてますが、まったくその通りです。(略) 誰でも、尊重され、大切にされたいからです。 心から関心を示せば、相手は大切にされていると感じます。 ※デール・カーネギーは、名著「人を動かす」の著者 |
| 2007-06-03 |
同じ人でもずいぶんイメージが違ってくるものです。 私はいつからか心の中に、 「短所→長所変換辞典」を持つようになりました。 例えば、 「おしゃべり↓ 話術がすぐれている・表現力がある・開放的・社交的」 「がんこ→信念がある・意思が強い」 「臆病→慎重・計画性がある」 「暗い、陰気→おとなしい・もの静か」 「行動がのろい→落ち着いている」 「優柔不断→柔軟性がある」 「だらしがない→おおらか」 「甘えん坊→人に近づき名人」 自分の性格を悪いとか嫌いだとか思って 悩んでいる人がいますが、 悩んでも変わるわけではありません。 それより、悩むエネルギーをよい面を磨くことに使えば、 自然とバランスのよい性格に変わっていくと思います。 |
| 2007-06-02 |
実行しなければ何の役にも立たない。 人間を価値づけるものは、 実行とその実績なのである。 |
| 2007-06-01 |
それを相手が望んでいるときに、 それに応じられるというのが理想的だろう。 大切なことは「さりげなさ」なのだ。 このさりげなさができるのは、じつは本当に相手の 立場を思いやっているからこそ可能なことなのだ。 また、その人自身が謙虚という美質を有していて 初めてありうることなのだと思う。 つまりは、相手に心の負担をかけぬよう心づかいしつつ、 その人のために何か手助けになることをしようとする、 レベルの高い善意の行為。 こういうことができる人は、人間社会における、 人と人との距離感の読める人である。 |