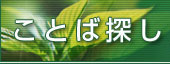■「今日のことば」カレンダー 2011年5月■
2025年 : 1 2 3 4 5 6 72024年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001年 : 11 12
| 2011-05-31 |
笑顔をつくることによって、脳の中の肯定的な感情を つくる部分が反応し、活性化される。 落ち込んだ時に元気を出したい場合やふだんの生活を 今より愉快にしたいなら、ともかくもっと微笑むこと。 テレビや劇場でコメディーやコントを見たり、 ジョークの本やユーモア小説を読んだりする。 ユーモアセンスあふれる人と友達になっていっしょに過ごす。 人生にもっと幸せがほしいなら、もっと微笑むこと。 自分の微笑みを改良するには、微笑みに使う筋肉を鍛え、 目を使って微笑むように気をつける。 楽しく感じていいときなのに、気分が陰鬱なときには、 無理矢理でも笑顔をつくってみよう。 |
| 2011-05-30 |
あなたの人生から「あなたに対する批評家」を消し去ろう。 これは、あなたの自信を奪う誰かさんだけでなく、 あなた自身に“批判的なあなた”も含まれる。 自分の作品や仕事が稚拙だとしても、まずはそれでよしとする。 才能がある場合でも、自分のすることやつくった物はすべて 立派でなければならないとか、はじめたことはすべて やり遂げなければならないとか、そういった考えは捨てる。 そうすれば、先へ進んだり、もっと独創的になったり、 まったく新しい方向に転換する自由が手に入る。 自由を自分に与えられない人は、創造的な仕事をする邪魔を わざわざ自分自身でしてしまっているのだ… 放棄しているといってもいい。 何事もひらめきを待つよりも毎日努力するほうがいい。 そして次のことは忘れないでほしい。 うまくできなくても、諦める必要はないということ。 |
| 2011-05-27 |
比較することなど絶対にできない。 できないけれど、比べたいのが人間だから、 無理やり「年収」や「学歴」、「家の大きさ」や 「持っているもの」など、さまざまな基準を作って、 比べようとする。 でも、本当のところは、やはり比べようがないのだ。 ならば、自分の人生や運命というものを肯定するしかない。(略) 人生は、しょせん、自己満足でしかない。 他人がどう判断するかより、自分で満足しているかどうか、 ということのほうが、人生にとっては重要だと私は思う。 |
| 2011-05-26 |
自己嫌悪になってしまうことがあります。 あなたが、会社の部長に怒っていたとします。 「ちょっとのことで、部長はすぐ怒る。ホント小っちゃい男!」 と部長の“すぐ怒る”という要素を嫌ったとします。 そして、あなたが後輩を持ったとします。 とてもドジな後輩を持ち、あなたの足をひっぱるんです。 「先輩、またミスちゃいました」 あなたは後輩に怒ってしまいました。 そんな時に自己嫌悪をしてしまいます。 ちょっとしたことで怒る部長のことを、小っちゃい男と 嫌っているにもかかわらず、部長と同じように、 ちょっとしたことで後輩を怒ってしまった自分を 嫌ってしまうわけです。 「こんなことで怒る私って、小っちゃいなー」と。 「人を呪わば穴二つ」といいますが、嫌った相手だけではなく、 嫌った相手を同じ要素を持つ自分を嫌ってしまうわけですね。 私たちは、自分を嫌ったり、責めないようになるために、 そして自分をもっと好きになるために、 誰かを許す必要があるわけです。 |
| 2011-05-25 |
待っている人の方が多いのではないか。 遠慮なんかしないで、どんどん話しかけたらいいのだ。 もし迷惑そうな顔をしたり、 遠ざけがっている素振りを見せるなら そのときは、相手の出方に任せて 追いかけなければよいだけだ。(略) こちらの気持ちをわかってもらいたければ、 相手のハラをさぐったりせず、こちらか飛び込んでいくべきだ。 すぐにわかってくれない人もいようが、 熱意と誠意が伝われば、やがて心は通じ合う。 たいていの人は、いつか必ず うち解けてくれる温かさを宿していると信じよう。 そう信じれば、仕事でも遊びでも 生きていく張り合いが何倍にもなる。 |
| 2011-05-24 |
経営コンサルタントのアドバイスにしたがって、 一流大学卒の新入社員50人集めて、 ユニークな新人研修を行いました。 これは一週間、ただただ誰でもできる使い走りの仕事を させるというもので、すると3日も経たないうちに、 「オレはこんなことをするために、この会社に入ったのではない」 と不平不満を口にするものが現れ始め、研修が終る頃になると、 大半の新人たちが同じ言葉を口にしたということでした。 しかし、その中で4人だけ不平不満を口にしないで、 黙々と仕事を行った新人がいました。そして、 その4人だけが出世コースを歩むなどして、 第一線で活躍するようになったのです。 |
| 2011-05-23 |
スティーブ・ジョブズ(アップルコンピュータ創業者)は、 最初から完璧を追求せず、「バグだらけの初期ソフト」 レベルから始める勇気をもっていた。 穏便にいえば、7割程度の完成度から始める勇気をもてるか、 どうかで、夢を描いてばかりの人と、行動に移せる人が 分れるのではないだろうか。(略) 夢を実現した人の軌跡をみると、 始めなければ始まらないから行動を起こしている人が多い。 大きな将来像を描いて、「これでいくぞ」と決めたら、 とにかく行動を始めるのだ。 行動してはじめて見えてくることがたくさんある。 それは机の前で夢を描いているだけでは、絶対に見えてこない。 夢を描いて準備をして、7割準備ができたら自分に ゴーサインをだしてはどうだろう。 |
| 2011-05-20 |
お金もエネルギーも、大事にすればするほど集まって来ます。 何かを買うとき、多くの人が、それを手に入れる喜びよりも、 財布からお金が出ていってしまう怖れや痛みをより 強く感じているのではないでしょうか? 財布の中身をみながら、 「また、1万円減った。残り2000円だ」 とか、「財布が軽くなった」と。 するとお金に対する不安や欠乏をいっそう感じて、 その恐れを実現したり、必要以上に欠乏を頻繁に感じて、 精神的ゆとりや自信も失いかねません。 惜しみながら出すのではなく、愛情を込めて、気持ちよく 支払うと、自分のもとにお金が返りやすくなるのです。 さらに素晴らしいことは、このように愛情を込めて、 支払って得たものを大切に使うと、その支払った価値の数倍、 数十倍の価値を得ることがたびたび起こります。 自分が今、お金を持っていること、使えることに感謝して、 気持ちよくお金を送り出しましょう。 |
| 2011-05-19 |
うじうじ悩むヤツが嫌いではない。 むしろそのほうが人間らしくて好きだ。 訪問販売の会社では、玄関先で追い返されても何とも 思わないようなタイプが出世するが、 そうした人たちは、無神経でジコチューな人が多い。 毎日毎日同じ満員電車に乗っていたら、たまには会社に行かず どこか遠くへ行ってしまいたいと思うのがまともなのだ。 そんなことを考えるのは心が弱いとか、鬱になるのは 根性がないからだと言う人がいるが、それは違う。(略) 無視されれば傷つくし、満員電車に乗れば不快感を感じる。 つらいことからは逃げ出したくなり、断れれば落ち込む。 そんな繊細な神経を持っているほうが、正常な大人だと思う。 些細なことで落ち込んだり、悩んだりする自分を、 一生懸命ほめたりなぐさめたり、励ましながら、 うじうじ生きていくのがまっとな人生なのではないだろう。 |
| 2011-05-18 |
真剣に自分に向き合って、 自分の人生の棚卸しをするつもりで、 よいところを探してみましょう。 最初は気乗りしなくてもかまいません。 気楽に書いてもいい、だまされたと思って試してください。 10個や20個なら簡単です。 100個というのがたいへんなことはわかります。 時間もかかります。 でも、やるだけの値打ちはあります。(略) 自分のよいところを見つけることは、 自分を肯定的に見つめる糸口になります。 明るい心は、まさにここからスタートするのです。 |
| 2011-05-17 |
なんでもいいからさ 本気でやってごらん 本気でやれば たのしいから 本気でやれば つかれないから つかれても つかれが さわやかだから 《道》 道はじぶんでつくる 道は自分でひらく 人のつくったものは じぶんの道には ならない |
| 2011-05-16 |
それに向って頑張るという成長意欲が必要だ。 しかし、ずっと上を見続けていると、人は疲れてしまう。 なぜなら、人生に「あがり」はないからだ。 人生で上を見続けるというのは、頂上のない山を、 上だけ見ながらひたすら登るようなものだ。 これはかなりしんどい。 山登りの楽しさは、高いところから下界を見下ろすことである。 上を見上げれば、まだ果てしなく登らなければならないと思って げんなりしてしまうが、下を見下ろせば、 もうこんなに登ったんだと達成感を得られる。(略) 人は何のために上を目指すのか? 本当は幸せな人生を手にするためであるはずだ。 それがいつの間にか、「上を目指して進むこと」 自体が目的になってしまい、「幸せを感じること」が 二の次三の次に、追いやられてしまっている。(略) この世は、上を見てもきりがないし、下を見てもきりがない。 ただ漠然と上に登っても、そこに幸せはない。 上から下を見たときに、初めて幸せは感じられるのだ。 |
| 2011-05-13 |
仕事や、恋愛でうまくいかなかった時に、 私たちは自分を責めてしまうことがあります。 「何で、もっと頑張らなかったんだろう、バカバカ私のバカ」 って感じです。 しかし、考えてみてください。 友人が彼氏に振られて落ち込んでいたとします。 そんな時にあなたが、 「何でもっと頑張らなかったの?バカバカ、あなたはバカよ」 といったとしたら、どうなりますか? たぶん友達は奈落の底にいくくらい落ち込むでしょう。 そして絶交されるかもしれません。 それくらいひどい言葉を 自分に向けて使っていることがあります。 ひどいことをいっていると感じないとしたら、 それはあまりにも自分を責めることをやり過ぎて、 麻ヒしてしまっているのでしょう。 お友達が落ち込んでいる時は、責めるのではなく、 優しくしてあげることが必要ですよね。 それと同じように私たちは自分が落ち込んだ時は、 自分を責めるのではなく自愛の心で、 自分に優しくしてあげることが必要なのです。 確実にこちらのほうが、 心のダメージの回復が早くなります。 |
| 2011-05-12 |
お互いに助け合う生き方はいいものです。 誰かとともに生きる生き方です。(略) 誰かに助けてもらったら 「迷惑かけて、すみません」ではなく、 「ありがとう」と感謝すればいいのです。 それが助けてくれた人への報酬になりますから、 「ありがとう」の感謝でその人が、 あなたを助けてあげようと思った善意の気持ちや労力、 あなたのために使った時間に報いてあげられるのです。 |
| 2011-05-11 |
身がもたないだけでなく、気もおかしくなってくる。(略) 結局は自分を信じ、やれることを 全力でやるしかないと割り切るしかないのだ。 暗い話題、イヤな話をいちいち気にしていたらキリがない。 そんななかでも明るい話題はつくれないか、 仕事を楽しくやるには、なにをどうしたらよいか、 そう考えることが大切だ。 |
| 2011-05-10 |
にこやかな人も好きだ。 「なんといい表情をしているんだろう」と、 つい羨ましく思うことがある。 できることなら自分もそうなりたいし、もっと人を、 笑わせるユーモア精神があればいいのにと思うことがある。 だが、どうもそれがうまくできないクチだと 自分ではわかっている。 人間だけが表すことができる笑顔をもっとふりまけたら いいのにと思いながら、それがあんまり得意でないから、 せめて不機嫌そうな表情だけはすまいと努力している。 笑顔のなにがいいって、それは言葉よりも、 もっとわかりやすいということだ。 地球にはいろいろな民族がいるけれど、 話しても通じないことも笑顔でならたいてい通じる。 |
| 2011-05-09 |
何事も、やってみなければわからないのがこの世の中です。 わからないからといって、「失敗するのでは」と 悲観的になって実行を躊躇したり消極的なれば、 失敗する確率が高まります。 逆に、「わからないからこそ可能性があるのだ」と 自分に言い聞かせて、前向きに取り組んでいくと うまくいく確率が高まってきます。 人間は心理の動物です。 何事もはじめから成功と失敗が別れているのではなく、 自分自身が「駄目だ、できっこない」と思えば失敗するし、 「絶対できる」と思えば成功するまで何度でもチャレンジするから 結果的に成功を手に入れるだけです。 この世に、最初から条件が整っていることなど まずありません。 自らが、どれだけ有利な条件を作り出せるかが 人間の器量だと思います。 |
| 2011-05-06 |
「助かったよ、ご苦労さん」 この一言で、苦労も吹き飛んでしまいます。 相談する言葉…「若い君の意見をききたい」 「あなたはどう思う?」 相談されれば、誰でも嫌な気はしない。 当事者意識が出てきて、やる気がでてくる。 期待と激励の言葉…「ここはひとつ、君に期待するしかない」 「頑張っているね」 こんな言葉をかけられたら、多少の心配は あってもおのずと元気と自信がわいてくる。 信頼する言葉…「ここは君に任せた、頼むよ」 「君ならきっとできるよ」 任されて、「よし、いっちょうやってやるか」 と頑張らない人はいないはずだ 誉め言葉…「よくやった」「ここがいいね、なんとも言えないね」 誉められれば、自信が湧いてきて、積極的になる。 この5つの言葉は、素晴らしい効果を発揮する 黄金の言葉と、言われています。 あなたは、「言葉のご馳走」を惜しんではいませんか? 言葉は使っても減らない大事な宝物です。 「言葉のご馳走」をケチらないように。 |