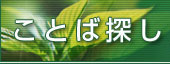■2008年11月13日の「今日のことば」■
前日のことばを見る 次のことばを見る|
仏教のお経の本に(阿弥陀経(あみだきょう))
こんな言葉がでてきます。 「青色青光(しょうしき・しょうこう)」 黄色黄光(おうしき・おうこう)」 赤色赤光(しゃくしき・しゃっこう)」 白色白光(びゃくしき・びゃっこう)」 どういう意味かといえば、ほとけさまのいる国 (極楽世界)に、はすの花が咲いています。 青・黄・赤・白のはすの花が咲いているのです。 そして、青のはすの花は青く光り、 黄色の花は黄色に光り、 赤いはすの花は赤く光り、 白色のはすは白く光っている… というのです。 みなさんは、青い花が青く光り、赤い花が赤く光って いるのはあたりまえではないか、と思われるでしょう。 どうしてお経は、わざわざそんなあたりまえのことを 言っているのか、ふしぎに思われるかもしれません。 (下に続く)
しかし、これはこう考えてください。
「青色青光。黄色黄光」の 「青色」というのは、「頭のいい子」 「黄色」は「頭のよくない子」だとします。 そうすると、これは、 「頭のいい子は頭のいい子としてすばらしい、 頭のよくない子も頭がよくないそのままですばらしい」 ということになるのです。 頭のよくない子が努力して、そして頭がよくなった時 すばらしい子になる、というのではありません。 頭がよくない子も、そのままですばらしいのです。(略) わたしたちは、頭のいい子のほうが 頭のよくない子よりもいい子である、怠け者より 努力家のほうがいい子だ、と思っています。 しかし、ほとけさまの国では、そうではありません。 ほとけさまにすれば、頭のいい子も頭のよくない子も、 努力家も怠け者も、泣き虫もおこりんぼうも、 みんなそのままですばらしいのです。 それが、 「青色青光。黄色黄光。赤色赤光。白色白光」です。 (ここまで引用) 私も好きな仏教言葉です。 青い花は青い花でよし、黄色の花は黄色の花でよし… 赤い花は赤い花でよし、白い花は白い花でいい… そして、自分は自分のままでよし、 自分以外の者にならなくていい… 自分の花を咲かせればいい、自分の色で… 少なくても、ほとけさまは、 そんな自分を、ちゃんと見ていてくださる… あたたかく、あたりまえに… |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||