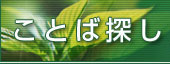■「今日のことば」カレンダー 2016年4月■
2025年 : 1 2 3 4 5 6 72024年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001年 : 11 12
| 2016-04-28 |
友だちは「つかれ離れず」でつきあいたい。 基本的に「友だちは去っていくもの」ですが、 死なないための人間関係は、できればずっとキープしていたい。 生きていくために 「しがらみ」はいらないけれど、 「つながり」は切らずにいたい。 それには2つのコツがあります。 まずは「縛りあわない」 日本人はとくに他人とのつきあい方がベタッとしがちで、 ちょっと仲よくなるとお互いに縛りあう傾向があります。 たまたま集まりに行かないと 「なぜ来なかったの?」「私のこと嫌いになったの?」 という具合に縛りあげられ、ひさしぶりに行くと無視される… そんな経験ありませんか?思春期の精神的に 不安定な中学、高校生ならそれも仕方ないでしょう。 けれど、30、40代の友人同士が縛りあうのは、 人間として未熟すぎます。 つかれ離れず、でいることがコツです。 |
| 2016-04-27 |
アウトプットを前提にしたインプットでないと意味がない。 いろいろな人から教えてもらったり、本を読んだりして 知識を身につけることは大切ですが、 それを自分の人生にいかしたり、実際の場で 役立つように使わなければ意味がないと思います。 知識を知識にとどめてはいけない。 実際にしなければ無意味だということです。 |
| 2016-04-25 |
あるベテランの脚本家の話。 「ドラマの主人公には共通する2つの条件があります。 1つは、ドラマはもめ事から成り立っているので、 トラブルを解決する能力のない者は主人公になれない」 実社会でも同じだと思います。 人間関係や仕事でも、うまくいっている間は能力は人間性は あまり関係ありませんが、トラブルや失敗したときに どう対応し、解決していくかで、その人の本性が試されます。 逃げずに、問題に真正面から取り組むことです。 もう1つの条件は、 「ドラマの主人公は、個性を生かしているからこそ 魅力的に見える。だから独自の人生観を持っていないと、 ドラマの主人公にはなれない」 これからは、差別化の時代ですから、自分しかできない能力、 自分が生まれてきた役割は何かを見極め、 それを磨いていかなければなりません。 |
| 2016-04-22 |
タンポポ魂 踏みにじられても 食いちぎられても 死にもしない 枯れもしない その根強さ そしてつねに 太陽に向かって咲く その明るさ わたしはそれを わたしの魂とする |
| 2016-04-21 |
一粒の花の種があります。 それを、机の上に置いて眺めているだけでは、 いつまで待っても花は咲きません。 適当な時期に、適当な土の深さに埋めてやる。 さらに、適当な雨露や陽光に恵まれて、 はじめて花が咲きます。 |
| 2016-04-20 |
優しい言葉をかければ、 信頼が生まれる。 相手の身になって 考えれば 結びつきが生まれる。 (老師/哲学者) |
| 2016-04-19 |
慈悲深き 友をもつは 人生の宝なり |
| 2016-04-18 |
パソコンでも受験でも、競馬や麻雀でも、僕は一度その対象に ハマりこんでしまうと、異常なほどに没入してしまう。 周りのことが何も見えなくなる。 なぜそこまでハマるのか、昔は不思議でたまらなかった。 でも、おそらくこれは、僕なりの生存戦略だったのだ。 なにかに没入することで、死を遠ざける。 死について考える時間を、可能な限り減らしていく。 僕は死を忘れるために働き、死を忘れるために全力疾走し、 死を打ち消すために充実させていたのだ。 自分が死ぬことについて、発作に襲われるほどの恐怖を 抱えている人は少ないと思う。 明らかに僕は極端だ。 |
| 2016-04-14 |
人の心はみな違い、それぞれ深いもの。 教えたり、言いつけたりすることは好みませんので、 それはしません。 人は話しているうちに自分で解決していくものですし、 それが真の答えになると思うのです。 ちょっと会って話を聞いただけで、 判断することは慎みたいものです。 |
| 2016-04-13 |
「いまと昔。どちらが良かった?」 すると、回答が真っ二つ。 A「昔は楽しかったな。ぼくも若かったし、景気もよかった。 日本にも元気があった」 B「そりゃ、いまだよ。なんてたって、いま、夢中にやってることが あるんだよ。金を積まれても若い頃には戻りたくないね」 統計をとると、昔派が8割。いま派が2割というところだろうか。 あなたは昔派?それともいま派? さて、この質問の意味がわかるだろうか? そう「昔は良かったよ」という人はいま、不幸なのである。 逆に「いまのほうがずっといいね」という人はいま、幸福なのである。 簡単な質問だが、いま、その人がどういう状況にあるか、 その人のツキはどうか、レントゲンのようにすべてを透けて見通せる。 怖いほど違いがよくわかるのだ。 |
| 2016-04-12 |
不思議なことです。 一日のほとんどを暗い気持ちで過ごしていても、 明るい気分で過ごしたたった1%の時間のほうを、 僕らは「本来の自分」だと感じる。 それはもしかすると、僕らは、 「明るい心の自分」こそが本来の姿であることを、 心のどこかで直観しているからかもしれません。 |
| 2016-04-11 |
敵をつくらないためには、日頃の振る舞いも大事です。 議論をしていても、徹底的に相手の息を根を止めないようにする。 必ず逃げ道を用意しておいて、相手が敗北感を持ったり、 相手から恨みを買わないようにする。 要は、相手に人前で恥をかかせないことです。 たとえば、会議の席で上司が漢字の読み方を間違ったとき、 みんなの面前で、 「凡例はボンレイじゃなくて、正しくはハンレイと読むんですよ」 とか、 「代替はダイガエじゃなくてダイタイです」 などと指摘したら、上司は赤っ恥をかかされてしまいます。(略) くだらないと思うかもしれませんが、こんな小さなことで、 いざというとき(それほど回数が多くないから「いざ」なのですが) に足を引っ張られるのは、もっとつまらないことです。 いざというときは、提案や企画を通そうとするときなどを ねらって、敵は足をすくいにきます。 肝心なときに泣かないためにも、 敵をつくらないようにくれぐれも注意してください。 |
| 2016-04-08 |
私たちは必要なことや大切なことに、時間や労力をかけないように なってしまっているように私には感じられます。 旅行に行っても写真は撮りっぱなし、お世話になった人への お礼状やお返しもしないまま、などということがあるのが その一例ではないでしょうか。 そのようなやり残し感は、非意識での心の不快として蓄積され、 ストレスや罪悪感となってしまいます。(略) 旅行の写真を整理したとき、旅という時間が締めくくられます。 お礼状やお返しを済ませたとき、ご恩を受けた時間が 締めくくられます。そのようなことをするのは、 清く正しいことであると、私たちの心は知っています。 ですから、そのような行動をすると、自分自身に満足します。 そのような時間を作った自分、その行動をすることのできた自分を 認めることができ、そんな自分のことが好きであると思えるものです。 それは、パーティが後片付けも含めてパーティの時間ということと 同じです。 「真の時間の締めくくり」に費やす時間は、 おそらく長くても半日。 数時間ですむことが多いことと思います。 するべき、したほうがいい、と思えることは、善は急げ。 行動に移しましょう。 やり残した感なく過ごすことは、豊かで幸せな人生を送る人の、 心のたしなみと言えるかもしれません。 |
| 2016-04-06 |
親しい友達といっても、夫婦といっても、 全く同じ経験を共有することはできませんから、 どうしても分からない部分があります。 浅いつきあいでは、気にならなくても、 深くつきあっていけばいくほど、 理解できない相手の部分が知らされます。 これは、努力不足というよりも、人間である以上 どうしようもないことなのです。 「どうせ、人間は分かり合えないのだ」と絶望し、 自分のカラの中に閉じこもって、周りをシャットアウトして しまいたくなることもあるでしょう。 そんな私たちに対して、お釈迦さまは、 「独りぽっちは、あなただけではないのだよ。 みんな独りぽっちで苦しんでいるのだよ」 と言われています。 孤独で苦しんでいるのは、あなただけではないのです。 自分が分かってもらえないと苦しんでいる時、 相手もまた分かってもらえないと苦しんでいるのです。 |
| 2016-04-05 |
人はだれでも、これまでの自分の行動を顧りみます。 あの時はこうしておけばよかったと後悔することもあります。 しかし100%ベストな選択なんてめったにないものです。 後になって悔いることを少なくするために、 その時点で最良だと思う選択をするしかないように思います。 仮に思い通りにならなくても、 そのときにベストだと思う選択をしていれば、 それほど後悔することはありません。 仕方なかったと諦めがつきます。 諦めがつかないのは、 ベストだと思う選択をせずに進んでしまった場合です。 100%ベストな状態とは「完璧」な状態のことです。 でもそれはあり得ないですから、完璧にやろうなどと思わずに、 まず動くことが大切です。(略) 動かなければ何も見えてきません。 まずは動くこと。 そこからいろいろなものが見えてくるのです。 |
| 2016-04-04 |
70歳過ぎて、長年続けた東京、明治座の公演をやめた時に、 これからの困難は認知症だと思ってさ、どんどん忘れていく、 そこへどんどん足していくのはどうだろうって。 認知症対策って、マイナスを心配せずに、プラスを考える。 それが大学受験のきっかけだった。(略) 昨年(73歳)「現役」で合格。 仏教大学は奥が深い。 授業はほぼ皆勤。 こんな面白いことを4年間で終えちゃてはつまらない。 仏教の勉強は8年間やりたい。(略) 夢はいろいろあります。 もっと勉強して、大学院出て、 ダメな生徒を教える教官になりたいね。 迷える子羊を集めて、教えることが1番勉強になります。 4月からの新学期が待ち遠しいなぁ。 コメディアン 萩本欽一さんのことば (東京新聞2016年4月2日 考える広場「はじめの一歩」より) |
| 2016-04-01 |
焦土となった敗戦の祖国へ引きあげてきたときも、 希望は何ひとつなかった。 それでもシドロモドロにぼくは生きのびてきた。 「今日いちにち生きられたから、明日もなんとか生きてみよう」 と思った。 漫画家としてやっとフリーになったが、まわりは 天才、鬼才、異才がひしめいていて、とてもかなわない。 おまけにぼくは多病で、病気ばかりしていたので前途は真っ暗。 それでもあきらめはしなかった。 今までなんとかなったのだから、 辛酸なめているうちになんとかなると信じていた。 心の奥底の部分が妙に楽観的でノンキなのである。 困ったものだが、なんとなくピンチを脱出して、 何とか生きのびることができた。 売り出したい、流行児なりたい、 異性にももてたいと思ったが、まるでダメだった。 「なんのために自分は生きているのか?」 と考えるのだが、よくわからない。 C級の漫画家として、わかのわからない人生が 終わるのだと思うと情けなかった。 ところが、大変遅まきながら 60歳を過ぎたあたりから、あまり欲がなくなった。 「漫画は芸術である」なんて えらそうなことを言わなくなった。 人生の最大なよろこびは何か? それはつまるところ、人をよろこばせることだと思った。 「人生はよろこばせっこ」だと気づいたとき、 とても気が楽になった。 |