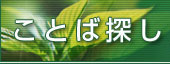■「今日のことば」カレンダー 2014年3月■
2025年 : 1 2 3 4 5 6 72024年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001年 : 11 12
| 2014-03-31 |
ゆったりとした時間の流れの中でとりとめもなくおしゃべりをする。 それが自分にとって幸せな時間であれば、無駄な時間ではなく、 とても価値のある時間の過ごし方ではないだろうか? 家族とすごすひととき、気の合う仲間と趣味について語り合うとき、 そこでは効率という物差しの世界では現れない、 自分の本当の姿が見えてくる。 その時間こそが、自分の人生を豊かにしてくれると思う。 確かに、単位時間あたりにどれだけ成果が上げられるかという 観点でみれば、無駄な時間かもしれない。 「ダラダラしゃべって、何を得たの?」 「その時間で、どれだけ稼いだの?」 と言われれば、たしかに成果はない。 だが、どれだけ楽しく過ごせたかという「時間の幸福度」 からすると、素晴らしく満たされた時間であることは間違いない。 よく「至福の時間」と言うではないか。 そのいう「時間の幸福度」は、効率とは無関係だと思う。 |
| 2014-03-25 |
「どう生きるのか?」という問いに 答えていくゲームです。 起きてくる出来事の意味が理解できないときもありますが、 それに囚われる必要はありません。 意味が理解できなくとも、その出来事には、 必ず意味があり、そしてその出来事を通じて、 私たちは成長できるようになっているのです。 「人生からの問いにどう答え、どう生きるのか」 そして、 「どう成長するのか」 そのゲームを存分に楽しもうではありませんか。 |
| 2014-03-24 |
何げない言葉が、相手のあなたへの評価につながっています。 よりアピールできる表現の事例を見てみましょう。 ×「一応考えてみました」 ○「私なりに時間をかけて考えてみました」 ×「二日間徹夜でした」 ○「時間がかかってしまいましたが、深く考えてみました」 ×「言われた通りにやりました」 ○「自分なりに考えてやってみました」 ×「△△さんに比べたらできたと思います」 ○「前回の提案は、◇◇が欠けていました。 今回はここを意識して作成してみました」 |
| 2014-03-20 |
自分の見本として常に競争相手がいるということです。 競争相手がいることで、私たちは自分に甘えることなく、 チャレンジ精神を持ち続けることができるからです。 競争相手はいつでも、自分を成長させてくれる とても有難い存在なのです。 競争相手は自分の努力がまだまだ足りないことを、 特に自分が気を抜いている時に教えてくれます。 そしてそれは相手にとっても同じことがいえるのです。 つまり、競争相手がいることで、お互いが どんどん成長していくことができるのです。 そもそも私たちは何のために競争するのでしょうか。 それは一流、本物を追求するためであって、 相手に勝つことが最終目的ではありません。(略) 身近にそのような競争相手がいない場合でも、 心配することはありません。 本当の競争相手は、誰にでもとても身近なところにいます。 それは、昨日の自分です。 |
| 2014-03-19 |
名古屋の「なつめ」は、銀座の名だたる店を差し置いて、 日本一と言われている。 「夜の商工会議所」という異名を持ち、 経済界の大物たちが集う店なのだそうだ。 ここのマダム、加瀬文恵さんは、 50年ほど前、弱冠19才でこの店を持った。 店の名前を決めるとき、こんなふうに思ったのだそうだ。 「銀座のクラブのようなフランス語のおしゃれな名前では、 名古屋の中小企業の社長さんたちは、経理のおばさんに、 伝票を出すのが恥ずかしかろう。 少し落ち着いた名前にしよう」 言ってみれば、《19の小娘》である。 なのに、顧客の気持ちをそこまで思える才覚に驚く。 押しも押されもしない日本一のマダムの座も、 そこから始まったのに違いない。 |
| 2014-03-18 |
ことばをご存じだろうか。 曰く(いわく)多くの人間が、七つまでの情報は、 一気に把握できるが、八個を超えるととたんに難しくなる。 また、六個の情報よりも、なぜか七個の情報の方が、 心理的な納まりがよく、忘れない。 子どもたちに何かを伝えるときは、 「六つのルール」や「八つのルール」よりも、 「七つのルール」の方が意識への納まりがよく、忘れにくい。(略) ヒトの脳には、 瞬時の認識のために使われるレジスター(入れ物)の ようなものがあり、そのうちの七つは、原初的なもので、 特に訓練しなくても、誰もが使える。 このため、七つの情報(七つでくくられる情報)までは、 人はつかみやすいのだ。 また、七つのレジスターが満杯になると、意識全体に、 「すべて取り揃った」「一巡した」という感覚をもたらす。 ヒトの脳は、百人百様のようで、意外にシンプルである。 |
| 2014-03-17 |
「人を大切にするって、どういうことなんでしょうか?」 それはいろんな答えがあるでしょうが、少なくとも 「人を大切にするって、どういうことなんだろう?」 と思っている人のほうが、思っていない人よりは 人を大切にするでしょう。 その人をどうやって大切にしようと思うのと、 その人から何を取ってやろうと思うのとでは、 関わり方がまったく違ってきます。 スタンスを決めることは重要です。 どうすれば人を大切にできるだろうか、 と思っている人は、少なくとも信頼されるでしょうね。 |
| 2014-03-14 |
ハッキリと刻まれています。 うまくいったことがあれば、また同じような決断をします。 失敗経験があれば、前回とは別の決断をします。 判断基準は、過去の経験から生じています。 しかし、私たちは、経験していないことを、 経験した範囲のなかで判断してしまうことがあります。 せっかくのチャンスを逃していることもあるのです。 ですから、過去に体験したことのないことは、 理屈で考えず、まず行動することが大切です。 新たなことに挑戦すれば、知らなかった 発想や方向性を発見できます。 その体験が自分を成長させてくれるのです。(略) どんなささいなことでもいいですから、昨日まで やったことのなかったことを、今日やってみてください。 |
| 2014-03-13 |
いや、ならないよ。 自分の人生は、自分で切り開くんだ」 「なんとかなる」という言葉には、両面がある。 何もしないで他人任せの「なんとかなる」では、 なんともならない。 やるだけのことをやってからの 「なんとかなる」とは、確実に一線を画す。 そこを勘違いしている人が多いのではないか。(略) 漠然と「なんとかなるだろう」と 思っているあいだは、何も変えられない。 自分自身が「こうしなければ」という意識を持った時に、 はじめて人は依存心を断ち切り、 自らの行動に変化があらわれるようになる。 何もしないで、「そのうちなんとかなるよ」と 言うのは、ごまかしだ。 ごまかしているうちは、何も変わらない。 |
| 2014-03-12 |
ある人がアメリカ人を家に招待し、ひととおり家の中を案内したとき 「この絵はなんてステキなんでしょう」 「このカーテンの色はいいわね」 「ステキな照明だこと!」 「壁紙の色が明るくていいわ」 などと、いちいちほめられて照れてしまうほどだった、 という話しを聞きました。 照れる思いを横に置いてそれらのほめ言葉を味わってみると、 一つひとつの言葉に決してウソがないこと、 「私はそれが好き」というその人の気持ちをストレートに 表現する言葉であることがわかってきました。 「こういう言葉の使い方はぜひ見習いたいなぁ」と、 その人は思ったそうです。 「私はそれが好き」という気持ちを、 押さえることなく、素直に表に出してみましょう。 出し惜しみをしたら、もったいないですよ。 |
| 2014-03-11 |
「苦」だから「不幸せ」と考えてしまう。 しかし、「楽」だけど「不幸せ」ということもあるし、 「苦」だけど「幸せ」ってこともある。 実は、「楽」だから「幸せ」って感情は 薄っぺらな幸福、偽りの幸福かもしれない。 「苦」だけど「幸せ」って感情は深い幸せ、 本当の幸福かもしれない。 「苦」であっても、 自分自身が生き生きした状態であれば、 それは幸せってことだ。 |
| 2014-03-10 |
「本当にがんばった」 と思える時期がどこにもなかったら、 「やるだけやった」 という自分の限界点らしきものを見極めなかったら、 その人はある種のすがすがしさを持って、 自分の人生を振り返ることができないだろう。 |
| 2014-03-07 |
どんなに悔しくても、いったん物事を あきらめなければいけない時があります。 自分は誠意を尽くしたのに、自分が悪いわけではないのに、 状況は悪化するばかりだと、複雑な気持ちをひきずりながらも、 「あきらめる」または「やめる」のが一番と判断して、 ダメージを覚悟で自分が身を引く決心をするしかない時もあります。 でも、それで何かさっぱりしたと感じるのなら、 その判断は正解なのです。(略) 潔く方向転換すればいいのです。 後々それでよかったと思えるはずです。 ここが悪かった、ああしていればよかった、これを損した、 あれを失った…などとダメージについて考えだしたらキリが ありませんが、いくら考えても元に戻せるわけではありません。 駄目なものにしがみつかないで、魂からの 「新しい道を切り開きなさい」というサインとして、 潔く方法転換すればいいのです。 それよりも、「これからプラスにしていけることはなにか」 ということにフォーカスして、自分に忠実に行動していけば、 モヤモヤした気持ちが晴れる頃には、 自分の求めていた新しい道が開けているでしょう。 |
| 2014-03-06 |
相手に依存するのではなく、自立をするということです。 相手の状態がどうであれ、 自分がすべきことにベストを尽くすということなのです。 一方、受け身なスタンスというのは、 相手に依存しているわけですから、相手が自分の期待どおりでないと、 それに不満を感じたり腹を立てたりします。 ある夫婦の会話で見てみましょう。 夜になって会社から帰宅してきた夫が、妻に尋ねます。 夫「例の郵便、出しておいてくれた?」 妻「あ、こめん、忘れてた」 夫「なんだって!(怒りながら)明日必着だったんだぞ。 楽しみにしていた懸賞だったのに、どうしてくれるんだ」 このケースで夫は、 「おまえのせいで、楽しみにしていた懸賞をあきらめなきゃいけない」 という被害者的なスタンスになっています。 つまりこれは、相手に依存しているわけですから 「甘えの心理」と言えます。 ここで主体的に考えになおすならば、 「郵便を締め切り前日に頼んだのがまずかったな。 次からは、もっと早めの時期に頼もう」とか、 「妻も忙しいだろうに、自分で郵便を出そうとしなった俺が 怠慢だったな」など、自分の行動を反省することができ、 この出来事から学びが得られるのです。 そして、こんな主体的な発想になると、 「そうだ!今から夜間窓口のある郵便局に行って、 速達で出せばいい」などの解決策も出やすくなります。。 |
| 2014-03-05 |
最初から、うまくいく人なんていないわよ。 だから、練習するんでしょ。 練習すれば、今より確実にうまくなるわよ。 楽しみにしているわ。 |
| 2014-03-04 |
故ハロルド・ジェニーン氏は、 「ビジネスの報酬は二種類のコインで支払われる。 それは、現金と経験。 まずは、経験のコインを取りなさい。 現金は後からついてくる」 という言葉を残しました。 私も同感です。 例えば、人を採用するとき。 その人が過去にいくら稼いでいたかなどは、あまり気にしません。 それより、どんな経験をしてきたかについては、 細かくチェックします。 成功を体験し、そのストーリーを語れる人がベストですが そういう人材が面接に来ない場合は、 逆に大きな失敗を経験した人を選んだものです。 「年収1000万円でした」「一部上場会社の部長でした」 とだけしか言えない人は、真っ先に候補から外します。 経験とは社内で過ごした時間のことではありません。 社内でもがき苦しんだ時間こそが「経験」と呼べるのです。 |
| 2014-03-03 |
苗を植えた直後に水をやったら、その後数日間は水をやらないのです。 水をやらないので、当然しおれてきます。 トマトやキュウリにしてみれば大ピンチの状態です。 そして、これ以上水をやらなかったからまずそうだと 思えるくらいのギリギリの状態になったら水をやるのです。 そのあとは、ふつうに水をやって育てます。 このようにして、植え付けたあとにしばらく水をやらなかった トマトやキュウリは背も高く、茎も太くたくましくなります。 植え付けたあとに毎日水をやったものと比べると、 明らかに違う成長ぶりです。 水がないというピンチの状態を経験したトマトやキュウリは、 水を求めて根を深いところまで張りめぐらすのです。 そして、土に深く根付くので、水分や栄養分を吸収する力が 強くなり、背の高い茎の太いものになるわけです。 これは、私たちに人間もいっしょですね。 私たちは、困難や逆境や悩みを経験するからこそ、 根を深く張って強く大きくなれるのです。 ですから、今、大きな問題や悩みを抱えている人は、 次のように考えてみてください。 「今、私は、目に見えないところで、 根を深く張りつつあるんだ」と。(略) 困難や逆境の中にあるときに問われるのは、あなたの心眼力です。 |